
お庭のリフォームで人気のゴムチップ舗装ですが、導入を検討する上で庭をゴムチップ舗装するデメリットについて気になっている方も多いのではないでしょうか?見た目がおしゃれで安全性が高いというメリットがある一方で、具体的な費用や単価、実際の施工方法、気になる水はけの問題など、事前に知っておきたい点はたくさんあります。
また、DIYは可能なのか、バーベQなどの火気は使えるのかといった疑問もあるでしょう。この記事では、そうした疑問を一つひとつ解消し、ご家庭に最適な選択ができるよう、後悔しないためのポイントを詳しく、そして分かりやすく解説していきます。
ポイント
- ゴムチップ舗装のメリットと後悔に繋がりやすいデメリット
- 施工にかかる具体的な費用や単価の目安
- DIYとプロの施工の違いと注意すべき点
- 舗装を長持ちさせるためのメンテナンス方法と耐用年数
庭をゴムチップ舗装するデメリットとメリット
- 安全性が高いなどのメリット
- ゴムチップ舗装にかかる費用
- 施工単価は厚みで変わる
- 下地が重要な施工方法
- DIYでの施工は可能か?
安全性が高いなどのメリット
庭にゴムチップ舗装を施す最大のメリットは、他の舗装材にはない、その卓越した安全性にあります。主原料であるゴム特有の弾力性が優れたクッション性を生み出し、万が一転倒してしまった際の身体への衝撃を大幅に和らげてくれます。
コンクリートやタイルでは大きな怪我に繋がりかねない場面でも、ゴムチップ舗装であればそのリスクを最小限に抑えることが可能です。そのため、小さなお子様が元気いっぱい走り回る遊び場や、足元がおぼつかなくなることもあるご高齢の方が歩行するアプローチなどにも最適な素材です。
実際に、全国の多くの公園、保育園や幼稚園の園庭、そして介護福祉施設などで広く採用されていることからも、その安全性の高さは公に認められていると言えるでしょう。
ゴムチップ舗装がもたらす主なメリット
- 安全性:優れた衝撃吸収性能で、転倒時の頭部や身体へのダメージリスクを軽減します。
- 歩行性:適度な弾力が膝や腰への負担を和らげ、長時間の歩行や立ち作業でも疲れにくい快適な環境を提供します。
- 透水性:内部に隙間を持つ構造のため水はけが良く、雨上がりでも水たまりができにくく、足元が滑る危険を減らします。
- 防草性:地面を隙間なくしっかりと覆うため、光を遮断し雑草の生育を抑制します。面倒な草むしりの手間から解放されるのは大きな利点です。
- デザイン性:カラーバリエーションが非常に豊富で、単色はもちろん、複数の色を混ぜ合わせたり、模様を描いたりすることも可能です。お庭の雰囲気や家との調和を考えたオリジナリティあふれるデザインを実現できます。
このように、安全性という最大の魅力に加え、日常生活の快適性やメンテナンス性の向上、さらには景観の美しさまで、多くの利点を兼ね備えているのがゴムチップ舗装の大きな魅力と言えるでしょう。
ゴムチップ舗装にかかる費用

多くの優れたメリットがある一方で、ゴムチップ舗装の費用は、一般的なコンクリート舗装やアスファルト舗装と比較すると高額になる傾向にあります。これは、ゴムチップという特殊な材料費に加え、それを均一に混合・敷設するための専門的な技術と手間が必要とされるためです。
費用相場としては、1㎡あたり約13,000円から23,000円が一般的な目安となります。ただし、これはあくまでゴムチップ舗装部分のみの価格です。
お庭の現状によっては、これ以外に追加の工事費用が発生することを理解しておく必要があります。
下地工事は別途費用が必要不可欠
最も注意すべき点は、ゴムチップ舗装は土の上に直接施工することができないという制約です。そのため、お庭が現在、土の状態(更地)である場合、舗装の土台となる安定した下地をまずコンクリートやアスファルトで造成する必要があります。この下地工事の費用(整地、残土処分、材料費、施工費など)が別途加算されるため、最終的な総額が想定よりも大幅に高くなるケースが多く、事前の見積もり確認が極めて重要です。
面積別・下地別の費用相場(目安)
下地工事を含めた場合の、より具体的な費用感を以下の表にまとめました。ご自宅の庭の面積と照らし合わせて、大まかな予算を把握するのにお役立てください。
| 面積 | 下地ありの場合 (ゴムチップのみ) |
コンクリート下地から施工 (合計費用) |
アスファルト下地から施工 (合計費用) |
|---|---|---|---|
| 5㎡ | 約6.5万~11.5万円 | 約9.5万~17万円 | 約8万~14万円 |
| 10㎡ | 約13万~23万円 | 約19万~34万円 | 約16万~28万円 |
| 20㎡ | 約26万~46万円 | 約38万~68万円 | 約32万~56万円 |
繰り返しになりますが、上記の金額はあくまで一般的な相場です。実際の費用は、土地の形状、高低差、既存の構造物の有無、そして依頼する業者によって変動します。後悔しないためには、複数の業者から現場調査に基づいた詳細な見積もりを取得し、内容を比較検討することが不可欠です。
施工単価は厚みで変わる

ゴムチップ舗装の施工単価を左右する最も大きな要因は、敷きならすゴムチップの厚みです。厚みが増せば増すほど、使用するゴムチップとそれを固めるバインダー(接着剤)の量が増加するため、当然ながら単価も比例して高くなります。では、どのくらいの厚みが必要なのでしょうか。これは、その場所を「何のために使うか」という用途によって明確に変わってきます。
用途別の推奨厚みと HIC値
- 歩行がメインのアプローチなど:10mm程度
日常的な歩行の安全性を確保しつつ、コストを抑えたい場合に適した厚みです。
この厚みでもゴムの弾力性は十分に感じられ、快適な歩行感を得られます。 - 子供の遊び場や遊具の下など:50mm以上
ブランコや滑り台といった遊具からの落下など、より大きな衝撃が想定される場所では、十分な厚みを持たせることが強く推奨されます。例えば、一般社団法人 日本公園施設業協会が定める安全規準では、遊具の高さに応じて衝撃を吸収するために必要な舗装の性能(HIC値:頭部損傷係数)が定められており、それをクリアするためには相応の厚みが必要となります。
このように、単に厚くすれば良いというわけではありません。コストと安全性のバランスを考え、用途に応じた最適な厚みを選ぶことが非常に重要です。専門業者と「この場所では子供がよく遊ぶので厚めにしてほしい」「ここは歩くだけなので標準で」といった具体的な使い方を相談しながら、ご自身の庭に最も合った仕様を決定しましょう。
下地が重要な施工方法

ゴムチップ舗装の美しい仕上がりと、10年以上にわたる長期的な耐久性を実現するためには、目に見えない下地部分の処理が最も重要であると言っても過言ではありません。前述の通り、ゴムチップはコンクリートやアスファルトといった、固く安定した下地の上に施工することが大前提です。もし、下地作りが不十分で表面が平滑でなかったり、強度が不足していたり、あるいは清掃が不十分だったりすると、数年で以下のような深刻な不具合が発生する原因となります。
- ひび割れ(クラック):下地の動きにゴムチップ層が追従できずに発生します。
- 表面の凹凸:下地の凹凸がそのまま表面に現れ、歩行性や水はけを悪化させます。
- 部分的な剥がれ:下地との接着が不十分な箇所から、ゴムチップ層が浮き上がり剥がれてしまいます。
これらの不具合を防ぐため、プロの施工現場では、下地を念入りに清掃・乾燥させた後、「プライマー」と呼ばれる特殊な接着剤を下地全体に塗布する工程を必ず行います。このプライマーが下地のコンクリートやアスファルトの微細な穴に浸透し、次に施工するゴムチップ層との間に強力な接着層を形成します。これが、舗装全体の耐久性を決定づける極めて重要な役割を果たすのです。
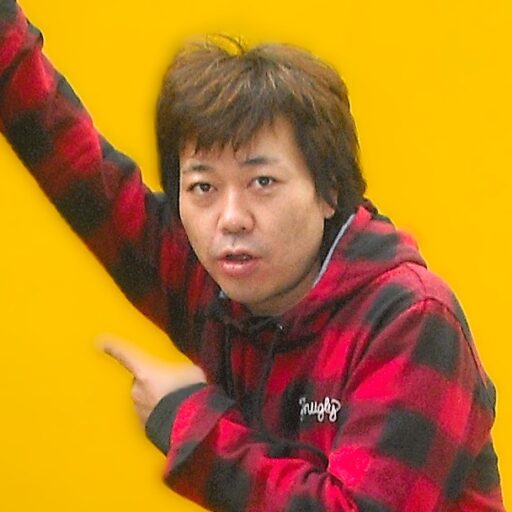
プロの業者は、長年の経験からその日の天候や気温、下地の状態を見極め、最適なプライマーの選定と塗布を行います。こうした目に見えない部分へのこだわりこそが、プロの仕事の価値であり、長期的な安心に繋がるのです。施工方法の中でも特に重要なポイントですね。
DIYでの施工は可能か?

近年では、ホームセンターやインターネット通販などでDIY用のゴムチップ舗装キットが手軽に購入できるようになり、「自分でやってみよう」と考える方も増えています。小規模なスペースであれば、専門業者に依頼するよりも費用を抑えられるという金銭的なメリットは確かにあります。
しかし、これまで述べてきたように、美しい仕上がりと十分な耐久性を確保するためには、下地処理から材料の混合、敷きならし、転圧まで、多くの専門的な技術と知識が求められます。そのため、安易な気持ちで始めると失敗する可能性が高く、DIYの難易度は非常に高いと言わざるを得ません。
DIYで起こりがちな典型的な失敗例
- 仕上がりのムラ:ゴムチップとバインダー(接着剤)の混合比率が不均一だったり、敷きならす厚みが場所によって違ったりして、見た目がまだら模様になったり、表面がデコボコになったりする。
- 耐久性の低下:下地処理の甘さや、コテで押し固める「転圧」作業の不足により、施工後わずか1~2年でチップが剥がれたり、ひび割れたりする。
- 硬化不良:バインダーの混合ミスはもちろん、施工日の気温や湿度を考慮しなかったために、いつまで経っても表面がベタベタして固まらない、あるいは硬化が早すぎて作業が間に合わない。
時間と費用をかけた結果、「やり直したいけれど、剥がすのも大変…」という事態に陥ることも少なくありません。以下の比較表でメリットとデメリットを冷静に比較し、ご自身のスキルや作業にかけられる時間などを考慮した上で、慎重に判断することをおすすめします。
DIYとプロ施工の比較
| 項目 | DIY | プロ施工 |
|---|---|---|
| 費用(5㎡) | 約6.3万円~(材料費のみ) | 約6.5万~11.5万円 |
| 仕上がり | 個人の技術に大きく依存し、ムラや凹凸が出やすい | 均一で美しく、長年の経験に裏打ちされたプロ品質 |
| 耐久性 | 施工精度が低いと、数年で劣化・補修が必要になる可能性が高い | 適切なメンテナンスで約10年以上の耐用年数が期待できる |
| メリット | 初期費用を抑えられる可能性がある、作業の達成感 | 高品質、高耐久、アフターフォローや保証がある、手間がかからない |
| デメリット | 失敗のリスクが高い、多大な手間と時間がかかる、保証がない | 初期費用が比較的高め |
結論として、「失敗したくない」「広い面積をきれいに長持ちさせたい」という場合は、初期費用がかかったとしても、経験豊富なプロの業者に依頼する方が、長期的に見て高い満足度と安心感を得られるでしょう。
庭をゴムチップ舗装するデメリットの詳細解説
- 紫外線による色落ちと汚れ
- メンテナンスの手間と頻度
- 水はけは下地の勾配が重要
- バーベキューなどの火気は注意
- ゴムチップ舗装の耐用年数
- 庭をゴムチップ舗装するデメリットまとめ
紫外線による色落ちと汚れ

庭をゴムチップ舗装する上で、最も多くの人が直面する避けられないデメリットの一つが、紫外線による経年劣化です。ゴム製品が日光に弱いことは広く知られていますが、屋外に施工されるゴムチップ舗装も例外ではありません。
日光に含まれる紫外線や、日々の雨風に常にさらされる結果、時間とともに「色落ち」が進行します。施工当初の鮮やかで美しい色は徐々にその彩度を失い、全体的に白っぽく褪せた印象になっていきます。
特に、赤や青といった色の濃いチップは退色が目立ちやすい傾向があり、「イメージと違ってきた」と感じる原因になりがちです。
ゴムチップの種類による耐候性の違い
ゴムチップには、主に廃タイヤをリサイクルした安価な「SBRチップ」と、耐候性に優れた合成ゴムである「EPDMチップ」があります。EPDMチップの方が紫外線による色落ちがしにくいため、美観を長く保ちたい場合は、初期費用は高くなりますがEPDMチップを選ぶのがおすすめです。
また、色落ちと並行して問題になるのが「汚れ」です。ゴムチップの表面は多孔質で細かな凹凸があるため、砂埃や土、落ち葉の破片などが隙間に溜まりやすいという構造的な特徴を持っています。この汚れが長期間蓄積すると、全体が黒ずんで見え、せっかくのカラフルなデザイン性を大きく損なってしまう可能性があります。
これらのデメリットへの対策として、前述の耐候性の高いEPDMチップを選ぶこと、そして定期的に水洗いなどの洗浄を行うことが有効です。完全に劣化を防ぐことはできませんが、適切な対策によって美しい状態をより長く保つことが可能になります。
メンテナンスの手間と頻度
ゴムチップ舗装は「一度施工すれば手がかからない」というメンテナンスフリーの舗装材ではありません。その美しい外観と、衝撃吸収性や透水性といった優れた機能を長期間維持するためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。この維持管理の手間とコストがかかる点も、導入前に理解しておくべき重要なデメリットです。
日常的なメンテナンス(ご家庭で可能)

日常的なお手入れは比較的簡単です。ほうきを使って表面の落ち葉や砂、ゴミを掃き出すだけでも、汚れの固着を防ぐのに効果があります。汚れが気になってきた場合は、ホースで水を撒きながらデッキブラシなどで軽くこすることで、多くの土汚れは洗い流せます。
ただし、高圧洗浄機の使用は注意が必要です。水圧が強すぎるとゴムチップ自体を剥がしてしまう恐れがあるため、ノズルを離して弱い水圧で使用しましょう。
専門的なメンテナンス(業者への依頼推奨)
.jpg)
より重要なのが、数年に一度の専門的なメンテナンスです。ゴムチップの表面を紫外線や摩耗から保護し、色落ちの進行を抑制、そしてチップ同士の結合力を回復させるために、2~3年に1回程度の頻度で「トップコート」と呼ばれる透明なウレタン系の保護塗装を施すことが強く推奨されています。
トップコートの費用は1㎡あたり約2,000円~3,000円が相場です。数年ごとに発生する定期的な出費にはなりますが、このメンテナンスを計画的に行うことが、結果として舗装全体の寿命を延ばし、将来的な全面張り替えといった大きなコストを回避することに繋がるのです。
水はけは下地の勾配が重要

ゴムチップ舗装の大きなメリットとして「透水性が高く、水はけが良い」と紹介されることが多いですが、これには一つ大きな落とし穴とも言える注意点があります。それは、舗装自体の水はけの良さは、その下にあるコンクリートやアスファルトといった下地の排水能力に完全に依存するという事実です。
ゴムチップの層は、言わば目の粗いスポンジのようなもので、雨水はスムーズにその層を通過します。しかし、その下のコンクリート下地が非透水性で、かつ水が流れるための適切な傾斜(水勾配)が設けられていなければ、行き場を失った水はゴムチップ層と下地の間に滞留してしまいます。
この「床下の水たまり」状態が長期間続くと、様々な問題を引き起こす原因となります。
排水不良が引き起こすトラブル
- 樹脂の劣化:常に湿った状態にあることで、ゴムチップを固めているウレタン樹脂が加水分解を起こし、劣化を早めてしまいます。
- カビ・苔の発生:湿気はカビや苔の温床です。表面に緑色の苔が生え、美観を損なうだけでなく滑りやすくなります。
- 凍害:冬場に滞留した水分が凍結・膨張することで、ゴムチップ層を内側から破壊し、ひび割れや剥離を引き起こす「凍害」の原因となります。
これを防ぐためには、施工の段階で下地に対して1.0%~2.0%程度のしっかりとした水勾配をつけ、排水桝や側溝へと確実に水を誘導する設計が絶対条件です。業者に見積もりを依頼する際は、「排水処理はどのように計画していますか?」と具体的に質問し、明確な回答が得られるかを確認することが、業者選びの重要な判断基準になります。
バーベキューなどの火気は注意

「新しい庭でバーベキューを楽しみたい」「夏には子供と花火を」と夢が膨らむ方も多いかもしれませんが、ゴムチップ舗装の上での火気の使用は、安全上の観点から原則として避けるべきです。これは、見落とされがちですが非常に重要なデメリットです。ゴムチップの主成分であるゴムや、それを固めているウレタン樹脂は、熱に弱い性質を持っています。(参照:株式会社 立成化学工業所 )
そのため、バーベキューコンロから落ちた火の粉や、高温になった調理器具(フライパンや鍋など)が直接接触すると、簡単に溶けたり、黒く焦げ付いたりしてしまいます。一度熱によって変質・損傷してしまうと、その部分だけを元の状態にきれいに補修することは極めて困難です。
見た目に醜い跡が残り続けることになってしまいます。
火気使用に伴う重大なリスク
さらに深刻なのは火災のリスクです。素材自体が可燃性であるため、最悪の場合、火災に繋がる危険性もゼロではありません。どうしてもバーベキューなどを楽しみたい場合は、コンロの下に広範囲にわたって不燃性のスパッタシート(溶接用シート)を敷く、あるいはコンクリート製の平板などを設置するといった厳重な対策が必要不可欠です。しかし、安全を最優先に考えるのであれば、基本的にはゴムチップ舗装が施されていない場所で行うことを強く推奨します。
ゴムチップ舗装の耐用年数
ゴムチップ舗装の一般的な耐用年数は、およそ10年~15年とされています。これは、適切なメンテナンスを行えば数十年以上持つこともあるコンクリート舗装などと比較すると、資産としての寿命はやや短いと感じるかもしれません。
この点も長期的な視点で考慮すべきデメリットです。もちろん、この「10年~15年」という数字はあくまで一般的な目安であり、実際の寿命は様々な要因によって大きく左右されます。
耐用年数に影響を与える主な要因
- 施工品質:最も重要な要素です。適切な下地処理、プライマー塗布、正確な材料配合、十分な転圧といった、質の高い施工が行われたかどうかが寿命を大きく決定します。
- 使用環境:一日中強い紫外線にさらされる場所や、人や車の通行が激しい場所では、当然ながら劣化の進行は早くなります。
- メンテナンス状況:前述の通り、定期的な清掃やトップコートの塗布が計画的に行われているかどうかで、耐用年数は数年以上変わってきます。
適切なメンテナンスを怠ってしまうと、10年を待たずして表面が硬化して弾力性を失ったり、チップがポロポロと剥がれ落ちてきたりする可能性があります。ゴムチップ舗装を導入する際は、初期の施工費用だけでなく、10年後、15年後の補修や再施工まで含めた長期的なライフサイクルコストを考慮して計画することが、後悔しないための賢明な考え方と言えるでしょう。
庭をゴムチップ舗装するデメリットまとめ

この記事では、庭をゴムチップ舗装する際のデメリットを中心に、メリットや費用、注意点について、より深く掘り下げて解説しました。
最後に、本記事の重要なポイントをリスト形式で改めて振り返ります。
最終的な判断を下すためのチェックリストとしてご活用ください。
- 初期費用はコンクリートやアスファルト舗装より高額になる傾向がある
- 庭が土の場合は下地工事の費用が別途必要になる
- 施工単価はゴムチップの厚みによって変動する
- DIYでの施工は可能だが難易度が高く失敗のリスクが伴う
- 紫外線や経年劣化による色落ちは避けられない
- 表面の隙間に汚れが溜まりやすく黒ずんで見えることがある
- 美観と耐久性維持のため定期的なメンテナンスが必要
- 2~3年ごとのトップコート塗布が推奨される
- 舗装自体の水はけは下地の排水性に依存する
- 下地に適切な水勾配がないと水が溜まり劣化の原因になる
- ゴムは可燃性のためバーベキューなど火気の使用は原則禁止
- 耐用年数は約10~15年でメンテナンス状況に左右される
- 高い安全性やデザイン性などのメリットも多い
- 費用や手間といったデメリットを理解した上で検討することが重要
- 後悔しないためには信頼できる専門業者への依頼が推奨される









