
ガーデニングのマルチング材として、くるみの殻が静かな人気を集めています。ナチュラルでおしゃれな雰囲気を演出できるその質感から、ホームセンターの園芸コーナーでも定番商品として見かけるようになりました。
しかし、その一方で「くるみの殻をガーデニングに使うデメリットはないか?」と導入をためらっている方も多いのではないでしょうか?特に、ナメクジなどの害虫が発生しやすくなるのではないか、という心配は、インターネットの口コミなどでもよく聞かれる不安要素です。
また、単に敷くだけでなく、具体的な使い道や、古くなった後の再利用方法、さらには土壌を豊かにする肥料としての効果があるのかどうかも、購入前に知っておきたい重要なポイントです。
この記事では、「くるみの殻をガーデニングに使うデメリット」というキーワードで検索されているあなたのあらゆる疑問に答えるため、くるみの殻の利点と欠点を徹底的に掘り下げ、失敗しないための賢い使い方を専門的な視点からご紹介します。
ポイント
- くるみの殻をガーデニングに使うメリットとデメリット
- ナメクジやシロアリなど害虫の具体的な対策法
- ホームセンターや通販での入手方法と価格帯
- 肥料としての再利用やその他の使い道
くるみの殻をガーデニングに使う魅力とデメリット
まず、くるみの殻をガーデニングに利用する基本的な知識として、その抗いがたい魅力(メリット)と、導入前に必ず知っておくべきデメリットの概要を整理して確認しましょう。
- ガーデニングに使う3つのメリット
- 基本的な使い方と敷く厚さのコツ
- ホームセンターでの価格と選び方
- ネット通販や100均での入手方法
ガーデニングに使う3つのメリット
くるみの殻がガーデニング資材として多くの人に選ばれるのには、他のマルチング材(ウッドチップ、バークチップ、砂利など)にはない、明確な理由が存在します。主なメリットは以下の3点に集約されます。
1. 景観の向上と防犯効果

最大の魅力は、そのナチュラルでありながら高級感のあるおしゃれな見た目です。一般的なウッドチップやバークチップとはまた違う、硬質で角の取れた立体的な質感が、庭全体をワンランク上の洗練された雰囲気(モダン、ナチュラル、リゾート風など)に仕上げてくれます。
また、非常に硬いため、上を歩くと「カラカラ」「カシャカシャ」という独特の乾いた音がします。この音は、防犯砂利と同様の役割も果たし、人や動物(野良猫など)の侵入を音で知らせてくれる副次的な効果も期待できるのです。
2. 雑草抑制と土壌保護(マルチング効果)
.jpg)
くるみの殻で地面を覆う(マルチングする)ことで、太陽光が土に直接届かなくなるため、雑草の種子の発芽を物理的に抑制します。これにより、ガーデナーの悩みの種である面倒な草むしりの手間を大幅に減らすことが可能です。
さらに、土壌保護の効果も絶大です。夏の強い日差しが土に当たるのを防ぎ、地温の急激な上昇を抑制します。
逆に冬場は、土の熱が放射されるのを防ぎ、霜や凍結から植物の繊細な根を守る保温効果も発揮します。土壌の水分蒸発も防ぐため、水やりの頻度を減らせる(乾燥防止)点も大きなメリットと言えるでしょう。
泥はね防止による病気予防
強い雨が降った際、土がむき出しだと泥水が跳ね返り、植物の葉や茎に付着します。これは見た目が悪いだけでなく、土の中に潜む病原菌(例:バラの黒点病菌など)が葉に付着する原因にもなります。くるみの殻は、この泥はねを効果的に防ぎ、病気のリスクを低減させる役割も担っています。
3. 卓越した耐久性と長期利用
くるみの殻は、主成分のリグニンやセルロースが非常に硬く結合しているため、他の木質系マルチング材(ウッドチップ、バークチップ)に比べて分解が極めて遅く、長期間利用できる点が最大の強みです。例えば、ソフトウッド(針葉樹)のウッドチップは1〜2年で分解が進み土に還り始めますが、くるみの殻(特に硬い鬼胡桃)は、環境にもよりますが数年〜10年近く原型を保つと言われています。
頻繁に補充する必要がなく、長期的なコストパフォーマンスに非常に優れている資材です。年月とともに色が褪せていく経年変化も、味わいとして楽しめます。
基本的な使い方と敷く厚さのコツ

くるみの殻の持つ優れたメリットを最大限に活かすためには、正しい使い方を実践することが何よりも重要です。特に「敷く厚さ」が、成功と失敗を分ける最大の鍵となります。
結論から言うと、推奨される最適な厚さは2〜3cm程度です。これには明確な理由があります。もし厚さが足りず1cm程度だと、殻と殻の隙間から地面が透けて見えてしまい、太陽光が漏れて雑草を抑制する効果が十分に発揮されません。
また、土壌保護の効果も半減してしまいます。逆に、5cmを超えるような極端な厚さで敷き詰めてしまうと、殻の層内部の風通しが著しく悪化します。
雨が降った後などに湿気が抜けにくくなり、内部が常にジメジメした状態になります。これがカビの発生や、本記事のテーマでもあるナメクジなど害虫の絶好の住処となってしまうのです。
失敗しないための重要な下準備
くるみの殻を敷く前には、まず敷設予定地の雑草を根こそぎ丁寧に取り除いておくことが大切です。その上で、防草シートを地面に敷き、その上にくるみの殻を設置する方法を強く推奨します。この一手間を加えることで、下からの雑草の突き抜けをほぼ完璧に防ぐことができます。さらに、くるみの殻が年月とともに土に沈み込んでいくのを防ぐ効果もあり、補充の手間やコストを抑えることにも繋がります。
ホームセンターでの価格と選び方

くるみの殻は、ガーデニング資材としてすっかり一般化しており、カインズ、コーナン、DCMグループといった大手ホームセンターの園芸用品売り場で容易に入手可能です。価格帯は店舗やブランド、容量によって幅がありますが、一般的な目安としては5リットル程度の小袋で500円~1,000円程度、20リットル袋で1,500円~2,500円程度が相場です。
当然ながら、容量が大きいほどリットルあたりの単価は安くなるため、広い面積に敷く予定がある場合は大袋を選ぶ方が経済的です。
ホームセンターで選ぶ際のチェックポイント
多くの商品は透明な袋に入っているため、購入前に中身の状態を自分の目で確認しましょう。
- 大きさ・色合い:殻の大きさは揃っているか。極端に細かく砕けて粉状になっていないか。
- 品質:湿気で濡れたり、袋の内側でカビが発生したりしていないか。
- 加工:洗浄・乾燥処理がされているか(ほとんどの商品は処理済みです)。
- 安全性:尖った部分を取り除く「角取り」加工が施されているか(子供やペットがいる家庭では重要)。
品質の安定性を目で見て選べるのが、実店舗であるホームセンターの最大のメリットです。
参考として、1平方メートル(1m×1m)に必要な量と費用の目安を以下の表にまとめます。
| 敷設する厚さ | 必要な土量(目安) | 必要な袋数(20L袋の場合) | 費用目安(20L袋/2,000円換算) |
|---|---|---|---|
| 3cm (0.03m) | 1㎡ × 0.03m = 30L | 30L ÷ 20L = 1.5袋 | 約3,000円 |
| 2cm (0.02m) | 1㎡ × 0.02m = 20L | 20L ÷ 20L = 1.0袋 | 約2,000円 |
ネット通販や100均での入手方法
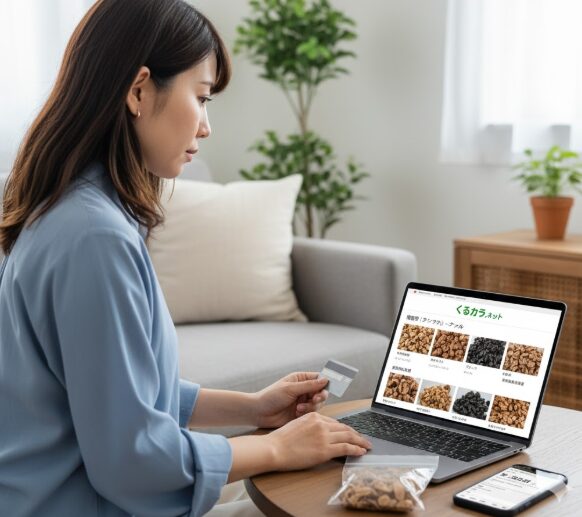
より専門的な商品(特定の品種や色など)を求める場合や、ホームセンターが近くにない方、あるいは大量購入を検討している場合は、オンラインショップが非常に便利です。特に「くるカラ.ネット」に代表されるような専門通販サイトでは、鬼胡桃(オニグルミ)や姫胡桃(ヒメグルミ)といった国産のくるみの種類、ナチュラルカラーや景観を引き締めるブラック系、丁寧な角取り加工が施された商品など、ホームセンターでは見かけない豊富な選択肢から選ぶことができます。
大量購入時の割引が適用される場合もあり、広い面積に敷きたい場合には最適な選択肢です。一方で、「まずはごく少量で試してみたい」「コストを極限まで抑えたい」といったニーズに応える選択肢として、100円ショップ(ダイソー、セリア、キャンドゥなど)の存在が思い浮かぶかもしれません。
ただし、これには重大な注意点があります。100均で販売されているくるみの殻は、そのほとんどがガーデニングのマルチング材としてではなく、インテリア用のデコレーション素材や、ハンドメイドクラフトのパーツとしての用途を想定したものです。
そのため、一袋あたりの内容量は数十グラム程度と極めて少なく、手のひらに乗るくらいの量しか入っていません。これを庭のマルチングに利用しようとすると、膨大な数の袋を購入する必要があり、結果としてホームセンターで大袋を買うよりも遥かに割高になってしまいます。
品質面でも、洗浄や乾燥がガーデニング用に比べて不十分な場合や、装飾用に防腐処理などが施されている可能性もゼロではありません。小さな観葉植物の鉢の表面を飾ったり、テラリウムの素材にしたりといった、限定的な使い方に適していると割り切るべきでしょう。
くるみの殻のガーデニングにおけるデメリットと対策
ここからは、この記事の本題である「くるみの殻をガーデニングに使うデメリット」と、それらを回避するための具体的な対策法を、より深く掘り下げて詳しく解説します。これらの懸念点を理解し、正しく対処することが成功の鍵です。
- ナメクジなど害虫の発生原因と対策
- シロアリを寄せ付けないための注意点
- カビの発生リスクと風雨による飛散対策
- 肥料としての効果と再利用の注意点
- その他の意外な使い道
- くるみの殻ガーデニングのデメリット総まとめ
ナメクジなど害虫の発生原因と対策

くるみの殻を導入する上での最大のデメリット、それはナメクジをはじめとする不快害虫の発生リスクです。ナメクジ以外にも、ダンゴムシやワラジムシ、場合によってはゴキブリなどの隠れ家になる可能性も指摘されます。
これらの害虫が発生する根本的な原因は、「湿気」と「隠れ家」という二つの条件が揃うことにあります。夜行性のナメクジやゴキブリは、日中の日差しや乾燥を極端に嫌います。
くるみの殻を地面に敷き詰めると、その下は太陽光が直接当たらず、一度吸収した水分が抜けにくい、暗くジメジメした環境が形成されやすくなります。この環境は、彼らにとってまさに理想的なシェルター(隠れ家)となってしまうのです。
殻と殻の間の複雑な隙間は、鳥などの天敵から身を守るのにも最適です。特に、前述の通り殻を推奨の2〜3cmより厚く敷きすぎたり、もともと日当たりや水はけが悪い場所に設置したりすると、この傾向はさらに顕著になります。
発生を未然に防ぐためには、彼らにとって快適な環境を作らないことが最も効果的です。
対策は「害虫が好むジメジメ環境を作らない」こと!
- 推奨の厚さ(2〜3cm)を厳守する:
これが最も重要です。通気性を確保し、過度な湿潤状態を防ぎます。 - 定期的に攪拌(かくはん)する:
最低でも月に1~2回、晴れた日が続くタイミングで、熊手や移植ゴテで殻全体を優しくかき混ぜ、空気に触れさせましょう。
これにより、内部の湿気を強制的に飛ばし、害虫が住み着いたり卵を産み付けたりするのを防ぎます。 - 銅製品の活用:
ナメクジは銅イオンを嫌う性質があります。
ナメクジから特に守りたい大切な植物の周りを、銅線や銅板(市販のナメクジガードなど)で囲うと、物理的なバリアとして機能します。
もし、すでにナメクジが発生してしまった場合は、夜間に懐中電灯を持って探し、割り箸などで捕殺するのが確実です。あるいは、ビールの匂いで誘引する「ビールトラップ」を設置するのも良いでしょう。
どうしても数が多い場合は、市販のナメクジ駆除剤を使用します。その際、ペットや小さなお子様がいるご家庭では、主成分がメタアルデヒドのものより安全性が高いとされるリン酸第二鉄のものを選ぶことをお勧めします
シロアリを寄せ付けないための注意点

ナメクジと並んで、特に木造住宅にお住まいの方が懸念するのがシロアリの発生リスクでしょう。「木」の仲間であるくるみの殻を家の周りに敷くことで、シロアリを呼び寄せてしまうのではないかという不安は当然のものです。
まず基本的な知識として理解しておくべきは、くるみの殻そのものがシロアリの主食になる可能性は極めて低いということです。日本で主に被害をもたらすヤマトシロアリやイエシロアリは、湿気を含んで柔らかくなった木材のセルロースを好んで食べます。
くるみの殻は非常に硬質で密度が高く、乾燥している状態ではシロアリにとって魅力的な餌ではありません。この点では、比較的柔らかく分解されやすいウッドチップやバークチップに比べて、シロアリに対する直接的なリスクは低いと考えられています。
しかし、リスクがゼロというわけではありません。問題となるのは、くるみの殻そのものではなく、それが作り出す「湿った環境」です。
シロアリは乾燥を極端に嫌い、公益社団法人日本しろあり対策協会が示すように、湿度の高い場所を好んで活動します。もし、くるみの殻を家の基礎部分に接するように敷き詰め、その場所が常にジメジメしている状態だと、シロアリが活動しやすい最適な環境を提供してしまうことになりかねません。
殻の下を隠れ蓑(蟻道=ぎどう=の代わり)として利用し、家の土台などへ侵入するリスクを高めてしまう可能性があるのです。
シロアリ対策で最も重要な絶対ルール
このリスクを回避し、安心してくるみの殻を使うためには、以下のルールを必ず守ることが重要です。「建物の基礎コンクリート部分から、最低でも30cm、できれば50cm以上は必ず離してくるみの殻を敷くこと。」基礎周り(犬走り)には何も敷かないか、敷くとしても砂利や砕石など無機質な素材を使用するのが最も安全です。基礎と土壌の境界線を常に目視で点検できるようにしておくことが、シロアリの早期発見にも繋がります。
カビの発生リスクと風雨による飛散対策
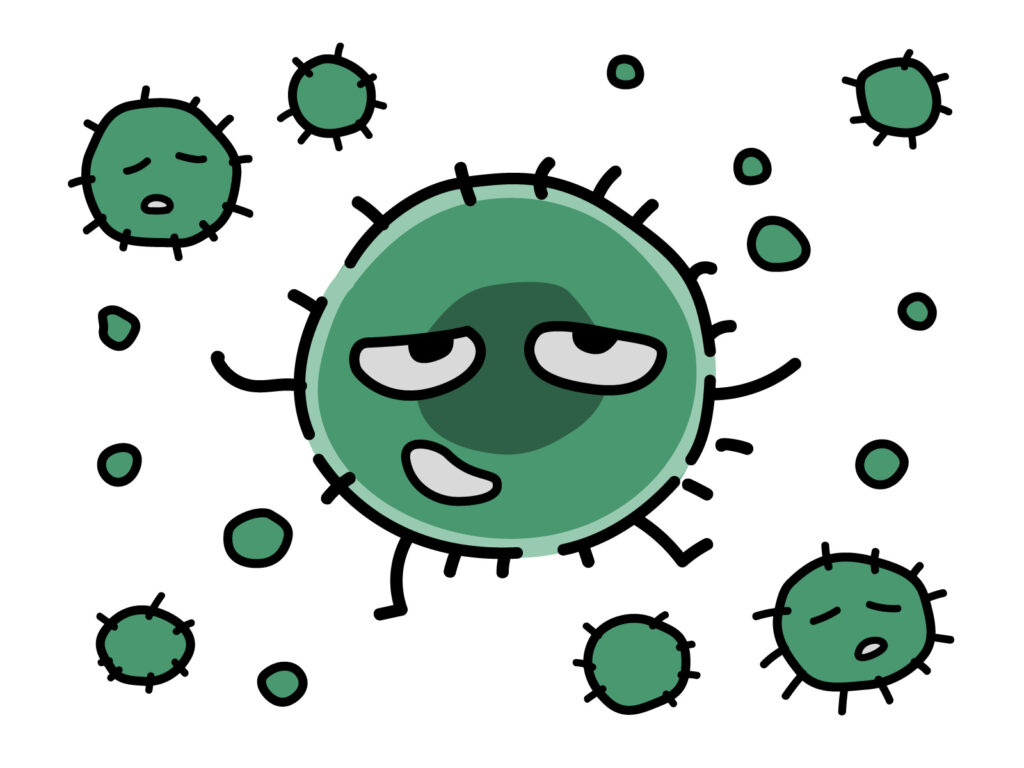
ナメクジの発生原因とも共通しますが、くるみの殻は有機物である以上、カビのリスクと無縁ではありません。特に梅雨の時期など、雨が続いて湿度が高く、風通しの悪い場所では、殻の表面や内部に白や黒のカビが発生することがあります。
これは見た目が悪くなるだけでなく、衛生的にも好ましくありません。対策は、これまでも繰り返してきた通り、「適切な厚さ(2~3cm)を守る」こと、そして「定期的にかき混ぜて湿気を飛ばし、通気性を確保する」ことです。
特に日当たりが悪い北側の花壇などでは、よりこまめな管理が求められます。また、もう一つの物理的なデメリットとして、強風や大雨による飛散・流出が挙げられます。
くるみの殻はウッドチップよりは重いものの、水に浮きやすく、軽量な素材であることに変わりはありません。台風やゲリラ豪雨、あるいは「からっ風」のような強風が吹く地域では、風で飛ばされて道路に散乱したり、大雨で雨水とともに流されて排水溝を詰まらせたりする可能性があります。
これを防ぐためには、敷設範囲の周囲をレンガやピンコロ石、あるいは市販のエッジング材(見切り材)などで物理的に囲うことが非常に有効です。プラスチック製、木製、金属製など様々なエッジング材があります。
これらで物理的な「ダム」や「防風壁」を作ることで、殻が意図しない場所へ広がるのを防ぎ、美しい景観を長期間維持できます。
肥料としての効果と再利用の注意点

「くるみの殻は植物由来の有機物だから、時間をかければ分解されて、土の良い肥料になるのでは?」と期待する声が聞かれます。しかし、この点に関しては、正確な知識を持っておくことが重要です。結論から言うと、くるみの殻をそのままの形で土に混ぜ込んでも、肥料としての効果はほとんど期待できません。
その最大の理由は、殻が非常に硬く、極めて分解されにくい性質を持っているからです。
くるみの殻の主成分は、木材の硬い部分を構成する「リグニン」や「セルロース」です。これらの物質は、土の中の微生物にとって非常に分解しにくいため、土中に埋めても数年から十年以上、ほとんど原型を留めたまま残ってしまいます。
そのため、植物が吸収できる形の栄養素(窒素・リン酸・カリ)が供給されることは、ごく長期間で見ない限りありません。それどころか、細かく砕いて土に混ぜ込んだ場合、分解の初期段階で微生物が活発化し、土の中の窒素を消費してしまう「窒素飢餓(ちっそきが)」を引き起こし、一時的に植物の生育が悪くなる可能性すらあります。
ジュグロン(アレロパシー)の影響は?
くるみの木には「ジュグロン(Juglone)」という、他の多くの植物の成長を阻害する効果(アレロパシー効果)を持つ天然の化学物質が含まれています。このため、「くるみの殻を敷くと植物が枯れる」という情報を見かけることがあります。ただし、市販されている洗浄・乾燥済みのくるみの殻に含まれるジュグロンの量はごく微量であり、マルチング材として地表に敷く程度であれば、ほとんどの植物に影響はないとされています。ジュグロンは主に根や葉から放出され、土に混ぜ込まない限り影響は限定的です。複数の研究(例:農研機構の研究や各種大学のレポート)では、トマト、ナス、ジャガイモ、リンゴなどが特にジュグロンの影響を受けやすいとされています。もし心配であれば、これらの感受性が高い植物の真下に大量に使用することは避け、影響を受けにくいとされるカボチャやニンジンなどの周りで試してみると良いでしょう。
もし再利用したいのであれば、物理的に細かく粉砕することが必須条件です。
その上で、落ち葉や米ぬか、生ゴミなど他の有機物と一緒にコンポスト(堆肥)に混ぜ込み、数ヶ月から一年以上かけて発酵・熟成させることで、初めて土壌改良資材の一部として機能するようになります。手軽な肥料とは到底言えないでしょう。
その他の意外な使い道

ガーデニングのマルチング材として役目を終えた後や、そもそもガーデニング以外でのくるみの殻の使い道もいくつか存在します。最も一般的なのは、インテリアやハンドメイドクラフトの素材としての活用です。
100円ショップで販売されているのは、主にこの用途です。クリスマスのリースやオーナメントの装飾、写真立ての飾り、あるいはテラリウムやアクアリウムの景観素材として使うと、ナチュラルな温かみをプラスできます。
また、ガーデニング関連では、多肉植物や観葉植物の鉢植えで、土の表面を隠す「化粧石(マルチングストーン)」の代わりとして使うのも非常に人気があります。水やりの際の泥はねを防ぎつつ、コバエの発生をある程度抑制し、何より見た目をおしゃれにできます。
さらに専門的な分野では、くるみの殻はその硬度と適度な油分から、金属や樹脂の表面を傷つけずに洗浄・研磨するための「ブラスト材(研磨剤)」として工業的に利用されています。また、高カロリーであることから、バイオマス燃料として活用する研究も進んでいます。
くるみの殻ガーデニングのデメリット総まとめ

最後に、この記事で解説してきた、くるみの殻をガーデニングで使う際のデメリット(懸念点)と、その対策法を一覧で総括します。
これらのポイントを理解し、正しく対策すれば、くるみの殻はあなたの庭を格上げする非常に有用な資材となります。
- ナメクジやゴキブリなど害虫の隠れ家になりやすい
- 対策は厚さ2~3cmを守り定期的に混ぜて湿気を飛ばすこと
- 家の基礎周りに敷くとシロアリを呼び寄せる環境を作る恐れがある
- 対策は建物の基礎から最低30cm以上離して使用すること
- 日当たりや風通しが悪いとカビが発生しやすい
- 対策は定期的にかき混ぜて通気性を確保すること
- 強風や大雨で飛散・流出する可能性がある
- 対策はレンガやエッジング材で囲いを作ること
- 肥料としての効果はほぼ期待できない
- 土壌改良には粉砕と長期の堆肥化が必要
- ジュグロンによる生育阻害の懸念は限定的
- 感受性の高い植物の土に大量に混ぜ込まないこと
- ウッドチップ等より初期コストがやや高い場合がある
- 耐久性が高いため長期的なコストで判断する
- 100均の商品はガーデニングのマルチングには不向きである









